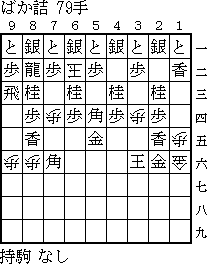
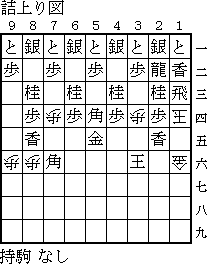
|
解答者が久々に20名を越えました。
大九郎氏の選題は七郎の選題と違い、人間の限界を越える解答能力を要求することはありませんので、皆さん積極的に挑戦しましょう。なお本稿は、大九郎氏多忙のため七郎が代筆しています。
◇解答者21名 全題正解2名
| 誤 | 無 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.56 |
| ② | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.33 |
| ③ | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.22 |
| ④ | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| ⑤ | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| ⑥ | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.71 |
| ⑦ | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| ① 神無三郎 『龍姫』 | ||
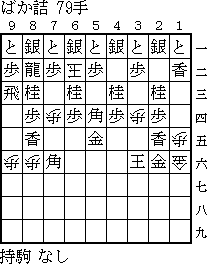
| 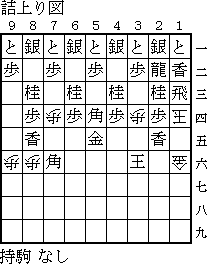
| |
原田清実 ― ほとんど一本道のような気もしますが、こういうの好きです。
☆易しくて気軽に取り組める三郎氏の「姫シリーズ」。今回は密室の玉を龍で追い回す趣向作です。
藤岡靖朝 ― 両端での合駒強要が見所の竜追い。
岩本修 ― あっという間の79手。
阿修羅 ― お城の中で追いかけ回しているという感じ。
☆密室型のばか詰で思い浮かぶのが飯田岳一氏の前衛賞作品(昭和53年99手詰)です。本作は飯田作のような凝ったパズルではなく、単純に手順の流れを楽しむ作品になっていると思います。
神無三郎 ― 客寄せができて良かった。次は「木馬姫」くらいがいいのかな。
☆まだまだ続く姫シリーズ。次作も楽しみです。
| ② 神無大九郎 | ||
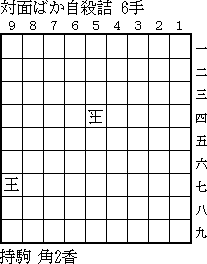
| 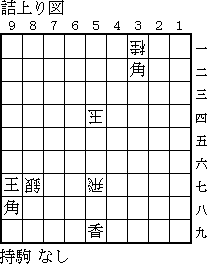
| |
筒井浩実 ― 角打桂対の詰め上がりとヤマを張ったら意外に簡単だった。全着手駒打ちというのが狙いか?
花田勉 ― 対面ば自6手でも全然易しくないから恐ろしい。最終手、攻方駒をわざと行き所のない効きにしてしまうのは、違和感があります。
☆キーワードは「角打桂対」。これを知っているかどうかで「簡単だった」と「全然易しくない」という対照的な2つの短評に分かれました。みなさんも是非この詰上りをを憶えて解図に役立てて下さい。
岩本修 ― 最終2手は記憶にあるが序の4手に工夫が感じられる。
神無大九郎 ― 4手詰(54→76として持駒角2)を2手逆算したのだが比較的うまくまとめる事ができたと思う。
☆この作者にはこの詰上りを使った超難解双裸玉があります。果たしてお披露目はいつになるでしょうか。
| ③ 神無太郎 | ||
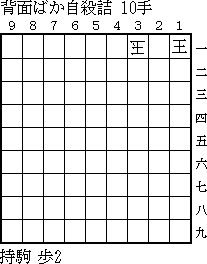
| 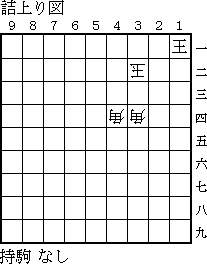
| |
☆持駒が歩2枚だけ。これで作品ができてしまうのが背面ルールらしいところです。
藤岡靖朝 ― 歩がナナメに成ることに気がつきにくい。
阿修羅 ― 詰上りを想像してやっと解くことができた。
神谷薫 ― この詰上りかっこいいな~。
☆本作の狙いはこの詰上り。つまり、
神無太郎 ― 王の開き王手はよくあるが玉の開き王手は珍しいと思う。
☆と、いうことです。背面ルールは単に対面の逆に過ぎないと思われる方もいるかもしれませんが、手順や詰上りの変化に富む点では、背面ルールの表現能力は対面ルールより上ではないかと私は感じています。
| ④ 神無七郎 | ||
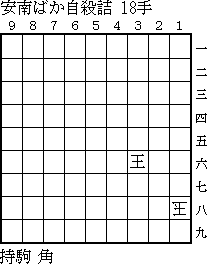
| 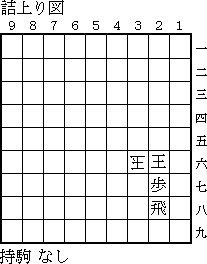
| |
☆まず最初にクイズを。この局面でルールが普通のばか自殺詰だったら何手で詰むでしょうか? 更に持駒に桂を何枚か加えて完全作ができるでしょうか?
☆答えは「34手」「完全作はできない」。
本作はこの調査中に、ふと思いついた作です。
駒井信久 ― 桂ではなく歩を利用するのが、ちょっと意外だった。
☆殆どの人が桂から先に考えたようですが、正解は歩。これも安南らしい詰上りのひとつです。
| ⑤ 神無七郎 | ||
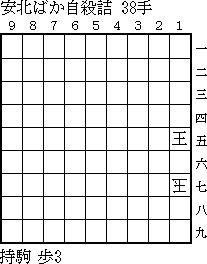
| 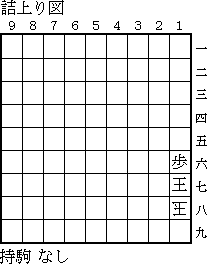
| |
☆④と対比で出題された本作。安南とは逆に玉が歩の下に潜る詰上りです。
岩本修 ― 山田嘉則の傑作を思い出す。
☆山田氏の作品も念頭にありましたが、本作の直接の元ネタは太郎氏と三郎氏の合作で11王33玉持駒歩2 14手という作品です。
☆さて、本作思わぬところに問題がありました。
半裸一族 ― 4手目27王以下36手の早詰。
☆つまり、4手目27歩が二歩になるため27玉とできるということなのです。
☆これは見落としではなく、出題時の注記漏れでした。神無一族は通常「利き二歩有効」で作品を作っています。仲間内で作品をやりとりする場合はそれで問題ないのですが、フェアリーランドで「利き二歩無効」を採用している関係上、パラ等でその旨を明示して出題しないと、作意が正しく伝わらないケースが生じてしまいます。
☆この作品の場合、作意解答が3名いて一安心。なお、半裸氏解はもちろん正解扱いです。
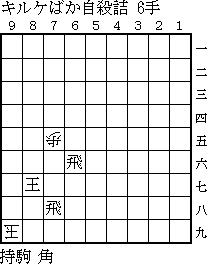
| 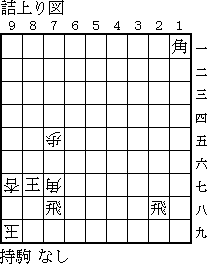
| |
積田隆介 ― 詰め上がりは想像できるが、この遠打は圧巻。
駒井信久 ― 11角最遠打がキルケを生かした妙手。
☆詰上りで77角を取ると、その角が22に復活して王に当たる。その22角の利きを消さないための11角の最遠打なのです!
神谷薫 ― 最後の2手で一気のラストスパート。このルールで後半の追い上げ型?は難解になりそう。
花田勉 ― 最終2手、取ったはずの駒にそのまま取られてしまうのが、いかにもキルケらしい。
☆構想部分に味を添えるのが取れない成香による詰上り。キルケの特徴を存分に生かした短編構想作です。
神無太郎 ― 復活駒の利きを保存するための限定打は三郎氏の発案。
☆三郎氏はこの手筋に「残夢剣」と命名しています。
半裸一族 ― 最後の/28飛は不要ですか。
☆はい、なくても正解です。
| ⑦ 神無右京 | ||
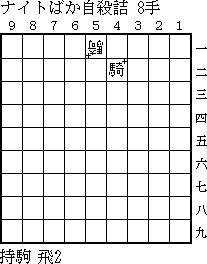
| 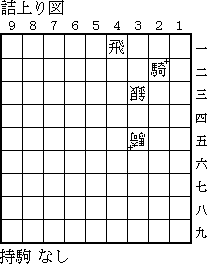
| |
☆一族の新人右京氏。素晴らしい作品での登場です。
某氏1 ― どうしても詰まない。玉合も考えたがダメだった。3枚目の飛があれば詰むのだが・・
某氏2 ― 全く詰みそうにない10手がやっと。
☆このように無解者続出。想定困難な詰上りに加え、そこに至るまでの手順も攻方の騎跳び2回を含み、決して平坦なものではありません。
花田勉 ― 2度の開王手することを想定して、飛打ちや騎跳びの場所を考えていた。
神無右京 ― 逆算が奇跡的にうまくいった作。趣向的手順、銀合、無駄のない詰上りとすべて気に入っています。
☆右京氏はフェアリー駒が得意で、今までの一族のメンバーとは違った個性を見せてくれると思います。
〔総評等〕
花田勉 ― 「背面」はともかく「安北」にはびっくり。「側面」とか「安東」「安西」なんてのもあったりして。
☆安東や安西の実例は見たことがありません。側面は作例があるようです。
なお、本稿はスペースの都合でルールの説明は省略しました。ルールについては6月号を参照して下さい。
Copyright(c) 2000 KAMINA Family